読書シリーズ⑱「人間臨終図巻」(上)
「人間臨終図巻(上)」山田風太郎 徳間書店
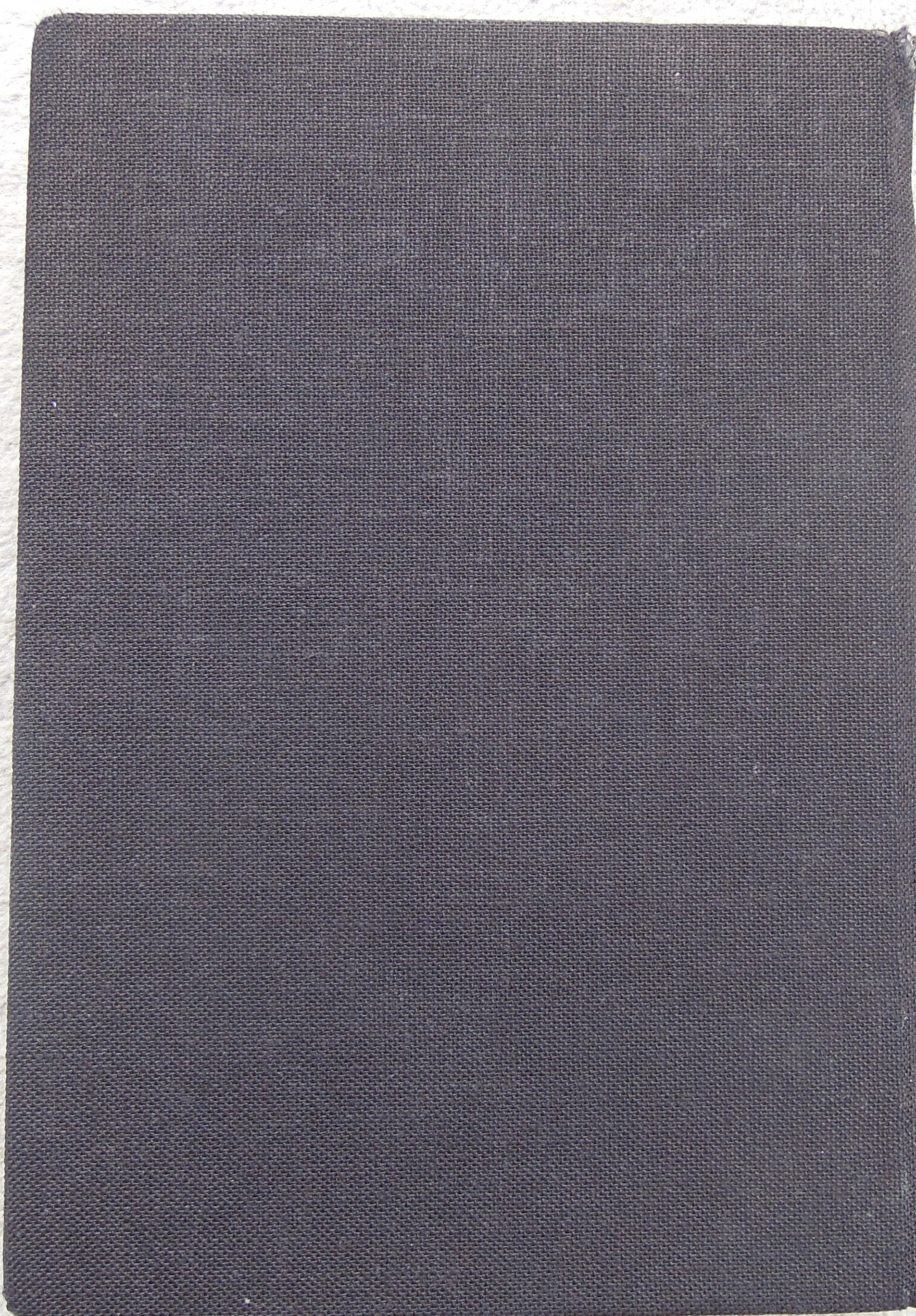
著名人の臨終時のありさまを事細かに調べてまとめたもの。
黒布張りの表紙には題名も著者名もなく・・不気味・・。
一読して「人間、死ぬ時が大切とはいうが、死ぬのも楽じゃあ無いなぁ~」という印象。
とにかく、昔の人は肺結核や梅毒で死ぬ人が多かったみたい。
それでは、現代では・・?やはり「ガン」だろうな~・・・。
特に印象に残ったのは、下記に引用した啄木の最後。
母親、啄木自身、奥さん・・みんな肺結核で働けない。とにかく、お金がなく「滋養のあるものを食べなさい・・」とアドバイスされても「お米が買えないんです・・」というありさま。
酷いの一言・・。
下記に、私の忘備録めもから一部引用してみます。
石川啄木(1886-1912)大正元年4月13日、肺結核・栄養失調で死去26歳
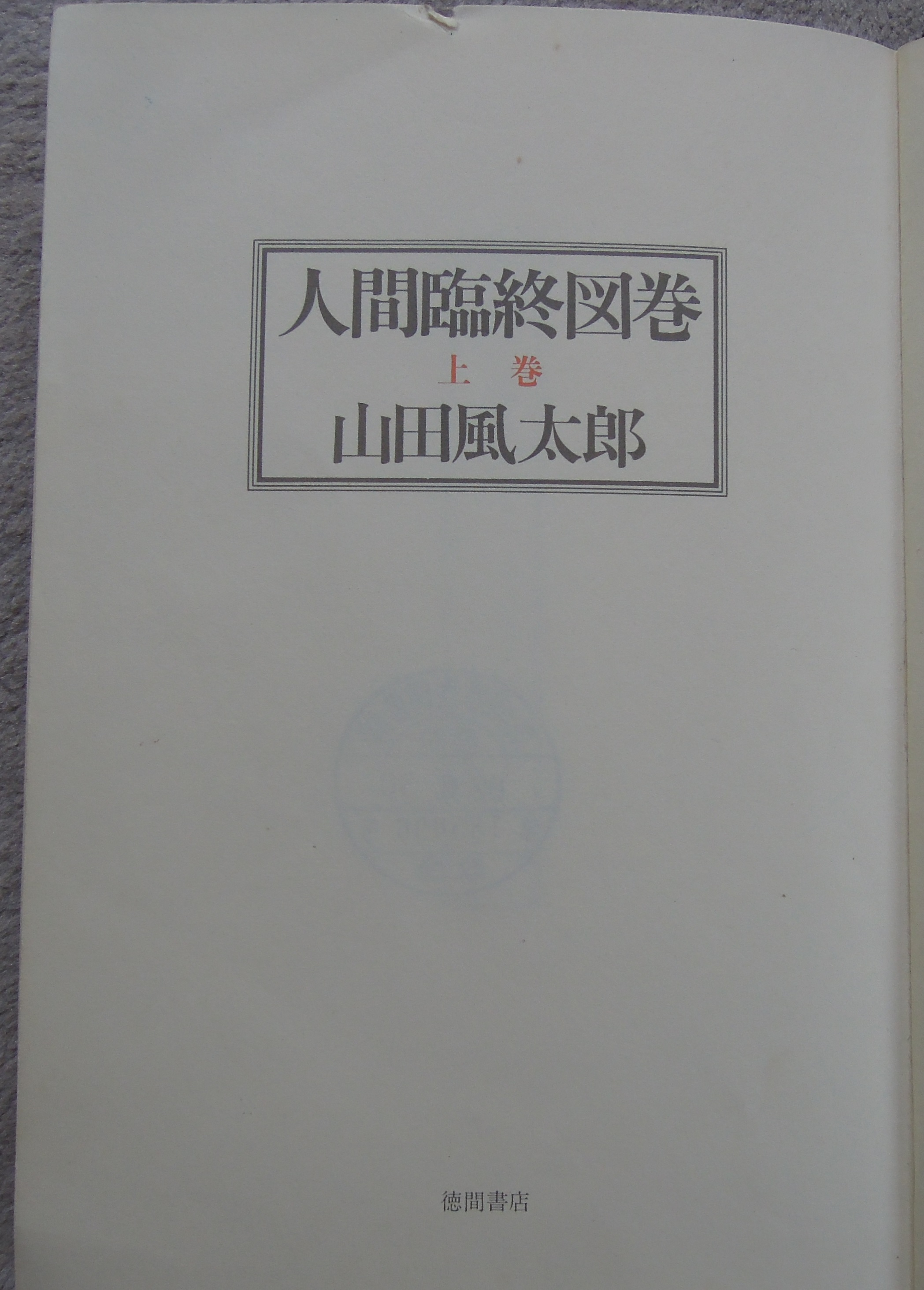
明治四十四年一月末から啄木は身体の変調をおぼえ、二月一日、大学病院三浦内科で診察を受けた結果、慢性腹膜炎と診断され、青山内科に入院した。
三月に一応退院したが、やがて肺結核の症状が明らかになった。七月に高熱を発し、病床についた。同時に妻の節子も健康を害し、これまた肺結核と診断された。炊事万端は老母の仕事となり、一家の窮状とそれによる不和の果てに、九月老父はいたたまれなくなり家出をした。
明治四十五年元旦、啄木は老母と妻に「元旦だというのに笑い声一つしないのは、おれの家ばかりだろうな」と、いった。
一月二十一日、森田草平が夏目漱石の奥さんからのお見舞いだといって十円を持ってきた。啄木は日記に書いた。「私は全く恐縮した。夏目さんの奥さんにはお目にかかった事もないのである。」
その金が一円しか残らなくなった一月二十九日、勤め先の朝日新聞社の同僚たちが集めた三十四円四十銭の見舞金が届けられた。
その翌日、妻は子供を連れていそいそとおもちゃを買いにゆき、啄木も「非常な冒険を犯すよな気で、俥に乗って」町へ出て、クロポトキンの『ロシア文学』や原稿用紙やノートを買い、四円五十銭使った。
「いつも金のない日を送っている者がタマに金を得て、なるべくそれを使うまいとする心!それからまたそれを裏切る心!私はかなしかった。」
二月中旬、こんどは老母が喀血し、この母が実は以前から肺結核の痼疾をもっていたことが明らかになった。小さな陋屋内は咳をし血をはくというありさまになった。
二月二十日(火)
「日記をつけなかった事十二日に及んだ。その間私は毎日毎日熱のために苦しめられていた。三十九度まで上がった事さえあった。そうして薬をのむと汗が出るために、からだはひどく疲れてしまって、立って歩くと膝がフラフラする。
そうしている間にも金はドンドンなくなった。母の薬代や私の薬代が一日四十銭弱の割合でかかった。質屋から出して仕立て直させた袷と下着は、たった一晩家においただけでまた質屋へやられた。その金も尽きて妻の帯も同じ運命に逢った。医者は月末払いを承諾してくれなかった。
母の様態は昨今少し良いように見える。然し食欲は減じた。」
啄木の日記はここで永遠に終わっている。
老母の病状はしかしそのころから急速に悪化し、三月七日に死亡した。
ついでに啄木の病勢も昂進し、前年家出をして北海道の知人の家に寄留していた老父は呼ばれてまた上京した。
そして、三月十三日、「読売新聞」に「石川啄木いよいよ重態」とあるのを見た同郷の友人金田一京助は、小石川久堅町の啄木の家に駆けつけた。
啄木は衰弱し切って、幽霊さながらの顔になり、京助の眼にも死期の近いことを悟らせた。啄木は、「いくら生きようたって、こんなですよ」と、夜具をあげて見せた。骸骨の骨盤に皮が張っているような腰が見えた。
「金を払わないから、医者も来てくれない」
と、彼はいい、京助がそのひどい栄養不良ぶりに、「医者よりも滋養物をとらなくちゃ」とつぶやくと、「滋養どころか、米がないの」
と、異様な笑いを浮かべて、頭をかいて見せた。
金田一は、脱稿したばかりの言語学の原稿を持って出版社へいって金にかえようとしたが、思うようにゆかず、家に駆けもどって、有金ぜんぶ――翌月分の生活費の十円――をかき集めて、また石川家へ走っていった。
啄木は枕の上で目をとじて、手を合わせてふし拝んだ。病妻の節子も枕元に座って嗚咽していた。
四月十三日朝、金田一は勤め先の国学院へ出勤しようとして、また石川家からの急報に呼ばれた。
玄関に節子が出て来て、啄木が昨夜から昏睡状態におちいっていて、ときどきうわごとのように金田一さんを呼んでくれと言っている、といった。
部屋に入ると、しゃれこうべのような啄木の、眼、鼻、口がただの穴のように見え、その穴の一つが、
「たのむ。・・・・」
と、からっ風のような声をもらした。
そこへ若山牧水がやって来た。
啄木夫婦は、京助に学校にゆくことをこもごも勧めた。
金田一京助は、二時間の講義ごとに二円もらうことになっていて、その二円が家計の上で重大なものであることを、彼らもしっていたのだ。どこか浮世離れした性格を持つ京助は、それで国学院へいった。
牧水は書いている。
「それから幾分もたたなかったろう。彼の容態はまた一変した。話しかけていた唇をそのままに次第に瞳があやしくなって来た。私は慌てて細君を呼んだ。細君と、その時まで私が来て以来次の間に退いて出て来なかった彼の老父が出て来た。私は頼まれて危篤の電報を打ちに郵便局まで走って帰って来てもなおその昏睡は続いていた。細君たちは口うつしに薬を注ぐやら、唇を濡らすやら、名を呼ぶやらしていたが、私はふとその場に彼の長女(六歳だったと思う)のいないのに気がついてそれを探しに外へ出た。そして桜の落花を拾って遊んでいた彼女を抱いて引き返した時には、老父と細君が前後から石川君を抱きかかえて、低いながら声をたてて泣いていた。老父は私を見ると、かたちを改めて『もう駄目です。臨終のようです』と云った。そして側に在った置時計を手に取って『九時半か』と呟く様に云ったが、まさしく九時三十分であった」
そして牧水は、
「よく安らかに眠れるという風のことをいうが、彼の死顔はそんなではなかった」と書き、「蒸し暑い日和で、街路には桜の花が汗ばんで咲き垂れていた」と、書いている。
――死後、日本の若者たちが「啄木歌集」に献げた印税の百万分の一でも生前に恵んでくれたら、と啄木の亡魂は歯噛みしているにちがいない。